わたしたちの安心して働きつづける生活する条件がますます奪われている。
今、行革の中で、平成17年度予算編成に当り「400億円の不足」が言われている。「赤字再建団体に転落する」という脅しの中で、ますますの賃金の切り下げ(退職条件の切り下げ・特殊勤務手当の改悪・寒冷地手当の改悪・基本給の切り下げ等)による人件費の削減が実施・企図されている。
1月17日に開催された『新世紀行革懇談会』でも『県の組織のより一層の民営化・スリム化』が求められている。『県の組織のより一層の民営化・スリム化』の手法としては、人員削減や経費削減手段として、① 組織・施設の廃止 ②市町村への移管や民間委託の推進、③ 指定管理者制度(※1)の導入 ④ 地方独立行政法人化(※2) ⑤ 市場化テスト(※3)の導入等がある。
※ 1 「指定管理者制度」とは、従来「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共団体等に限られて(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が2003年6月13日公布、同年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられるようにする指定管理者制度が設けられた。これにより、管理委託をしている「公の施設」については、施行日から3年以内(2006年9月1日まで)に、原則として指定管理者制度に移行することとなった。 現在66の県施設が対象、また現在直営の「公の施設」として132施設に対してこの制度を導入する検討等を県当局が現在行なっている。
※ 2 「地方独立行政法人」とは、試験研究機関、大学、地方公営企業法適用事業などを対象にした「地方独立行政法人法案」は、一昨年7月に自民党・公明党の与党が成立を強行し、昨年4月に施行された。地方独立行政法人は、『公務員型』と『非公務員型』の二つの制度を置くとしているが、この選択は設置団体の判断に委ねられ、いずれの法人職員も理事長が任命することになる。法人設立時に該当職場に所属する公務員は、別に辞令を発せられない限り自動的に法人の職員となり、「非公務員型」法人の場合には、公務員の身分を失うことになるなど、職員の身分や権利、労働条件にかかわる重大な問題を持つ性格のもつ。
※ 3 「市場化テスト」とは、公共サービスの提供について、間と民が対等な立場、透明・中立・公正な条件のもとで競争入札を実施し、価格と質の面でより優れた主体が落札し、当該サービスを提供していく制度。民間が事業を落札するとこれまでその事業を担ってきた公務員は、配置転換、民間への移転その他身分に重大な変化が生じることになる。
1月27日、石井隆一知事は「このままでは新年度予算が組めない」として、3年間を期間とする一般職3%、管理職5%の賃金切下げ提案を行なった。さらに、2月2日に開催された知事提案説明会では、赤字財政に至った原因を棚上げし、一方で、「ますますのスリム化・効率化で行革を推進し、事業費を創り出す」とする行革断行宣言を行なった。ますます激しさを増す行革攻撃に抗する闘いは今からである。
加えて、現在、解雇・退職条件の改悪提案を受けている業務公社職員の状況は人事ではなく、まさに明日はわが身に関わる問題である。
いま、進む市町村合併の影響で、県から市への事務移譲が図られ、組織の縮小が進んでいる。そして「道州制」(府県合併)の動きも加速している。
【賃金切下げと当面する課題】
◇ 新研修制度の問題点
◇ 評価制度の導入試行実施の問題点整理
◇ 平成17年度実施に係る定数機構行革案 (12月3日及び1月17日提示)
□事務・・・計28名の削減
県税事務所の統合 △14名 別紙のとおり ※10月より
企業診断業務の外部委託 △1名 (診断業務担当等)
計量検定業務の体制見直し △2名 ※H18年4月以降さらに△3名
港事務所のあり方 伏木港事務所 △1名 (用地業務の減少により)
伏木港事務所及び富山港事務所の兼務解除し管理局に集中
中部厚生センター本所 △3名
八尾支所 △4名
砺波厚生センター福祉課 △3名
□技術・・・計27名の削減
農業改良普及体制の見直し △7名 ※順次H20年度までに△25名
※林業普及指導体制の見直し △6名 ※H18年度~H20年度までに△6名
引船業務のあり方 △1名
中部厚生センター本所 △4名
八尾支所 △14名
富山土木センター建築課 △1名(建築)
※今年4月に現在外郭団体に派遣されている事務職12名を県に引き上げる話も進んでいる。
◇ 要求をみんなで確認し、どこから反撃するか?
(1)職場からの取り組みの具体化
① 県の職場で安心して今後も働きつづけるために、『譲れない要求』は何か。
② 職場からの話し合いから要求を確認する。
③ 確認された要求を所属長からの上申及び分会から地区・協議会・本部に上げる。
(2)確認された一つひとつの行動をみんなで精一杯取り組もう。
評価制度については、本庁など一部職場で問題点などを洗い出す為に行った結果の総括なしに、平成17年4月から全職場で評価制度を試行する。
これは「県政に責任を持つ態度」ではない。失敗を職員のせいにしないでもらいたいものである。
額に汗して働くものが上記のように粗末に扱われていいのだろうか。それぞれ家族があり生活がある。一方的に切り下げられて甘受する方が問題と思う。それこそ民間では倒産である。身も心も奴隷根性になってはいけません。「問題」を問題として捉え意見反映ほをすることが社会を良くする第一歩。県民のみなさん良く考えてください。
下記の事業は地財危機のなか急いで作らねばならないものなのか疑問がある。
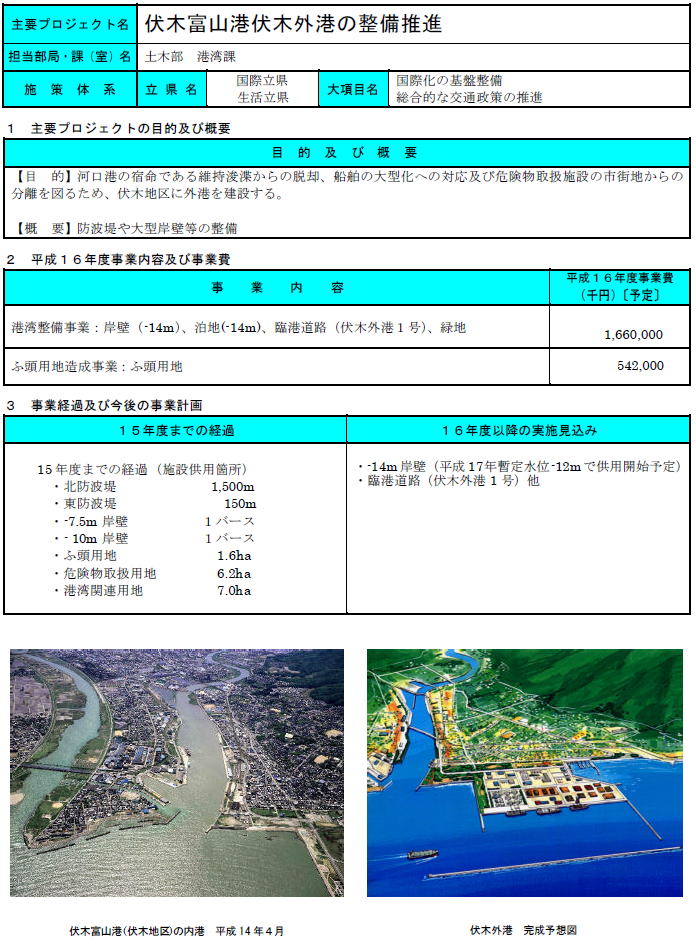
戻る